いざ、その分野の看護をするってなると・・・緊張と吐き気でヤバくないですか?
分かります!私もそうです。
なので、
今日は精神科看護師になる人必見!
とりあえず、これだけ抑えとこ!!な病気だけ絞って!
メチャクチャ簡単にかみ砕いて解説していきます(^^)/
精神科看護師必見!知っておくべき病気TOP10
統合失調症
現実感覚が鈍くなり、幻覚や妄想を抱くことがある病気です。
双極性障害
うつ病と躁病の両方の症状を持つことがある病気です。
うつ病
気分が落ち込んで、やる気が出ない、眠れない、食欲がないなどの症状がある病気です。
依存症
日常生活に害を及ぼす習慣を辞められない病気です。
不安障害
強い不安や緊張が長く続き日常生活に害を及ぼしてしまう病気です。
強迫性障害
強迫観念と強迫行動です。強迫観念とは、不合理で反復的な思考や恐怖の感情を指し、患者はこれらの思考から逃れられない苦痛を感じます。強迫行動は、不必要な反復行動や儀式行動のことであり、これらの行動を実行することで不安を軽減しようとします。
摂食障害
食事摂取や体重管理に異常な関心や行動が見られる心理的な障害です。
認知症
脳の機能が障害されることによって、記憶力や判断力、言語能力などが低下する状態を指します。
発達障害
神経発達において生じる個別の特性やパターンによって特徴付けられる障害の総称です。主な発達障害の種類には、自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害、知的障害などがあります。
パーソナリティ障害
個々の人格形成や行動パターンに関わる精神疾患です。その特徴として、持続的なパターンの形成や認識の歪みがあります。さまざまなタイプのパーソナリティ障害が存在し、それぞれに特徴的な行動や思考のパターンが見られます。
看護は何したら良いの?
では・・・肝心の看護師は何をしたら良いの(;´・ω・)?
について、取り敢えずの入り口用としてメチャクチャ簡単に説明していきますね。
統合失調症
患者さんが幻覚や妄想を抱いている場合、現実を共有することが大切です。また、患者さんが自分自身の感情をコントロールできるようにサポートすることも重要です。

双極性障害
躁病の場合は、患者さんが自分自身を傷つけないように注意することが大切です。
うつ病の場合は、患者さんが自分自身を責めないようにサポートすることも重要です。

うつ病
患者さんが自分自身を責めないようにサポートすることが大切です。また、患者さんが自分自身の感情をコントロールできるようにサポートすることも重要です。
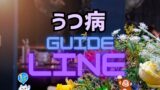
依存症
依存症の場合は、依存対象を断つことが難しいため治療には時間がかかることがあります。患者さんが依存対象を断とうとしている場合は、その決断を尊重し、サポートすることが大切です。
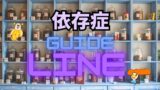
不安障害
不安障害は、不安が過剰に出現する病気で、不安感が日常生活に支障をきたすことがあります。看護師は、患者さんの不安感を軽減するために、落ち着いた環境を提供し、時間をかけて十分に話を聴くことが大切です。

強迫性障害
患者の特徴を理解し、患者の気持ちを受け止める時間を持つことが大切です。また、待つという接し方をすることも有効です。強迫行為が長引いても、待つ時間を持つことが大切です。無理に、こうしなさい、と指示的になるのは良くありません。患者は、自分のルールがあるため、そのルール通りに動かないと、辛く、ルール通りに動く事も辛いのです。矛盾していますが、そこをよく理解しましょう。

摂食障害
患者の身体的な状態や栄養状態を評価し、適切な食事計画や運動計画を立てることが大切です。 また、患者の自己肯定感や自尊感情を高めるために、心理的なサポートやカウンセリングも必要です。 患者の食事摂取や体重管理に対する認識や感情を理解し、共感的に話を聴くことも重要です。

認知症
患者の記憶力や判断力、言語能力などが低下する状態に対応することが必要です。 看護師は、患者さんの個性や生活歴を尊重し、安心できる環境を提供することが大切です。 また、患者の自立した生活を支援するために、日常的な活動や趣味などを一緒に行うことも重要です。

発達障害
患者の個性や能力を尊重し、そのニーズに応えることが大切です。また、患者のコミュニケーションや社会性をサポートすることも重要です。

パーソナリティ障害
患者の個性やニーズに応じて対応することが大切です。また、患者との信頼関係を築き、自己肯定感や社会適応力を高めることも重要です。患者が自分自身の感情をコントロールできるようにサポートすることも必要です。

まとめ
さて
どうでしたか?
めちゃくちゃ簡潔に書いてみました。
なんとなく精神科看護師の入り口としてイメージしてもらえたなら幸いです。



コメント